イスラエルが建国されてから今年5月が七十周年、この年に合わせてでしょう、ダニエル・ゴーディス著”Israel: A Concise History of a Nation Reborn“の邦訳版を、ミルトス社が4月に出版しました。
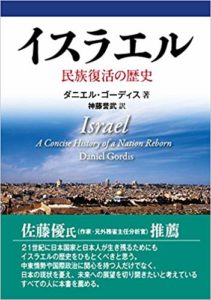
「イスラエル ――民族復活の歴史」(アマゾン)
近現代イスラエル全史について、これが決定版、これからしばらくの間は定番となるであろうと評されているようです。著者のダニエル・ゴーティス氏について、エルサレム・ポスト紙は、「世界で最も影響を及ぼす五十人のユダヤ人の一人」に挙げているとのこと。デニス・ロス元大統領補佐官は、「イスラエルについての良書を挙げるなら、この一冊」と言っているようです。私は、それとも知らず読み進めましたが、今日、完読して、確かにかなりの良書だと思いました。
良書を読むことは骨肉になる
良書と呼ばれているものに触れるのは、自分の肥やしになります。近現代のイスラエル通史について言うならば、以前、当ブログでも「イスラエル全史(マーティン・ギルバード著)」をお薦めしました。そして現代のイスラエル人の多様性を若い世代の生活を中心に親近感を抱けるように紹介している本として、「イスラエル人とは何か(ドナ・ローゼンタール著)」も紹介しています。そして戦史として、圧倒的にお薦めしたい本は、独立戦争を描いたノンフィクション小説「おおエルサレム!」ですが、圧巻でした。ユダヤ側だけでなく、アラブ側、パレスチナ側、米国政府内など、登場人物をそれぞれの立場から生きた人間として描いてくれています。そして、六日戦争を同じようにあらゆる側面から描き出している「第三次中東戦争全史(マイケル・オレン著)」は、六日戦争史の定番と言われています。そしてヨム・キプール戦争については、「ヨムキプール戦争全史(アブラハム・ラビノビッチ著)」の、エジプトからとシリアからの戦車戦の詳細な描写は圧巻でした。
こういったものが骨肉として、今のイスラエルを見る時に大きな役割を果たし、そして信仰者としては、聖書にある世界を見て行くのにとても大きな助けになります。本書も、その中の大きな一つになりました。
ダニエル・ゴーディス氏による天才的論評
 本書がそれほど評判が高く、良質なものであることを知らなかったのですが、邦訳版が出版されてから、ダニエル・ゴーディス氏の他の中東情勢についての英文記事を読んで、度肝を抜きました。(エルサレム・ポストとブルームバーグ誌の定期的なコラムニストらしいのですが、私が読んだのはこの記事。)彼のすごさは、「心を知っている」ということでしょうか。表に出て来る中東ニュースの情報をただ紹介するのでもなく、表面的な、お手軽な分析を施しているのでもなく、イスラエルに内在する心の深い部分から描き出し、そして歴史的視座を持ち、今の状況がその歴史の中でどこに位置しているのかを、いち早く織り込めるスゴ技です。そして、ぶったまげたのは、それがまさに、聖書の預言者たちが叫んでいた言葉に呼応するものだったことです。
本書がそれほど評判が高く、良質なものであることを知らなかったのですが、邦訳版が出版されてから、ダニエル・ゴーディス氏の他の中東情勢についての英文記事を読んで、度肝を抜きました。(エルサレム・ポストとブルームバーグ誌の定期的なコラムニストらしいのですが、私が読んだのはこの記事。)彼のすごさは、「心を知っている」ということでしょうか。表に出て来る中東ニュースの情報をただ紹介するのでもなく、表面的な、お手軽な分析を施しているのでもなく、イスラエルに内在する心の深い部分から描き出し、そして歴史的視座を持ち、今の状況がその歴史の中でどこに位置しているのかを、いち早く織り込めるスゴ技です。そして、ぶったまげたのは、それがまさに、聖書の預言者たちが叫んでいた言葉に呼応するものだったことです。
近頃のニュース解説を読んだり聞いたりしていると、腹が立つことがよくありませんか?あまりにも表面的、断片的な報道で、相手が生の人間で、何をもってそんなことを言ったりやったりしているのか、何も考えずに他虐的に論評するのみです。けれども、彼には政治家にも誰にも、過去の歴史の人物にさえ「同情」する能力を持っています。それゆえ、今、起こっている混沌とさえ見える複雑な情勢を、一筋縄のストーリーとして矛盾なく、混乱なく、浮かび上がらせることができる卓越した能力を持っていることが分かりました。
本書の最後にある訳者解説の中に、まさに著者本人がそのことに留意して書き記したことが書かれています。「一般の若者を対象に、長過ぎず、面白くて、学術的にも裏付けられたイスラエルの通史、それも事実の羅列ではなく、それがなぜ起きたのか、当時生きていた人々の内面、その実感が伝わるような書き方を心掛けた」(474頁)
全く頭を白紙にすれば、今のイスラエル・中東情勢が分かる
日本では、おおよそイスラエルを取り巻く情勢を正しく見ている人は僅少です。なぜかというと、あまりにも我々、日本人が近代において国が通って来た歴史と異なり、どんな歴史観や政治観の眼鏡を付けても、どこにも当てはまらないからです。まずもって、日本民族がその存在そのもの、あってはならないという生存権の否定をされた歴史を持っているでしょうか?まず、ここから出発点が違います。ですから、全く前提知識を無くして、初めから読み進めて行く必要がありますし、本書はそれを許してくれます。読み始めると、引きこまれるようにして次の時代の章へと読みすすめることができます。ちょうどドラマや映画、小説などの「伏線」のように、初めに出て来る、シオニズムの著名な思想家や政治家、詩人の言葉が、最後の最後に、また蘇るかのようにつながっているのを知ります。そうすると、今のイスラエルとパレスチナの関係も、手に取るように分かってくるようになっています。
私も、上記にあるようにいろいろな本を読みましたが、事実の羅列としては知っていたことも、「ああ、だからこんな思想があったのだ」とようやく理解できました。シオニズムにはいろいろな形態がありますが、テオドールの政治シオニズムを始めとして、文化シオニズム、労働シオニズム、また修正シオニズム、そして後に台頭する宗教シオニズムもあります。それぞれ、なんとなくは分かっていたのですが、それがくっきりと、分かりすぎるぐらいに分かりました。
ユダヤ人の悩みや自問を聞くことができる
私がイスラエルを取り巻く中東情勢の中で、日本人による解説を見聞きする時に腹立たしくなるのは、「あまりにも明快に答えを出す」ということです(関連記事「ここが変だよ!池上彰さん その1」)。日本人にとりあえず理解したという「気持ち」にさせるために、偏って、歪んでいる情報や見解を所々に入れています。しかし、世界で起こる事象の全てについて言えますが、ましてや中東情勢のような、輪をかけて複雑で深淵な内容を取り扱う時、「そのまま問題提起して、一人一人に悩ませ、考えさせる」ということを敢えてしなければいけない、と思っていました。
まさに、本書はそれを、描きに描き切っています。訳者解説によると、それこそユダヤ教的な書き方らしく、「「答え」よりも「問い」に関心を寄せる学習姿勢も窺えてイスラエルが抱える問題を率直に指摘している。言うなれば、各テーマの記述は著者の最終的な「解答」というよりも、読者に投げ掛ける「問題提起」として捉えたほうがいいのかも知れない。」(474頁)ということです。これは、ユダヤ教のラビでもあられたイエスご自身にも、また同じくユダヤ教ラビであった使徒パウロにも見える問いかけであり、パリサイ派のユダヤ人が「なぜ、あなたがたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。」と言って、彼らが手を洗わないことを咎めた時に、イエス様は、「なぜ、あなたがたも、自分たちの言い伝えのために神の戒めを破るのですか。」と逆質問をしておられるところにも、見られるものです(マタイ15章2‐3節)。
ユダヤ人の悩みとは、「弱々しく黙して生きる」生き方から、「たくましく、自信と尊厳をもって、健常に生きる」生き方への発展。また、「律法をひたすら守る」という「宗教的な生き方」ではなく、自由に物事を考えて、世界の一員として認められるような「世俗的な生き方」への脱却であったようです。例えば、1903年にロシアで起こったキシネフの虐殺において、詩人ハイム・ナフマン・ビアリクが激しく憤ったということが、シオニズムの原点の一つになっていることを描いています。
ビアリクの憤りは、次にユダヤの伝統それ自体に向けられた。ビアリクの”描写”によると、惨事の後、祭司の末裔であるこれらの男たちは、床の上に半死半生で痛ましく横たわっている妻たちの身体を跨いで、ユダヤ教ラビのもとに駆け寄り、質問する。
「妻は、私にとって、不浄(けが)れていますか」
―そんなことが大事なのか。ビアリクの叫びが聞こえるようだ。愛する者たちが、殴り倒され、傷つけられ、強姦され、地面に横たわっているというのに、お前たちの関心事はただ一つ、ユダヤ教の律法の問題、今後も妻と床を共にしてもいいか、ということなのか。お前たちの人間性はどうなってしまったんだ。いったいお前たちは、何者になってしまったんだ、と。・・・
祖国を離れた流浪の生活がユダヤ人から奪ったのは、強靭さや勇気だけではない、とビアリクは主張する。人間としての感覚を蝕んでしまった。流浪の生活がユダヤ人を破壊してしまった。・・つまるところビアリクは、ユダヤの伝統がユダヤ人の人間性を破壊した癌だ、と言うのだ。(58頁)
これが、ある意味でシオニズムとは何かを分かり易くさせる、心の叫びであると言えます。しかし、歴史の各コマで達成できないことへの葛藤があります。例えば、六日戦争後、第六章で「占領という重荷」で取り扱います。六日戦争によって、彼らが長い歴史の中で確保したかったもの、ゆまり、安全と自信と誇りと国際的認知でした。しかし、この勝利によって、戦争前に受けていた実存的脅威と同じぐらいの脅威を作り出してしまったと気付いた、としています。また、最後の第18章では、ここ最近に至っては、初めのシオニズムでは考えられなかったような、次世代のユダヤ教への伝統への回帰と、世俗と宗教の融合が見られるそうです。そこから脱却したはずのシオニズムは、脱却したゆえにユダヤ教の伝統に回帰したとも言えます。超正統派の急激な人口増加、宗教過激派が出てきたことなどの問題を最後に取り上げています。
イスラエルの救いの各部分を体現しようとする人々
聖書信仰、ことにイエス・キリストの福音を信じ、この方の再臨をもってイスラエルも回復すると信じている者にとっては、それぞれのユダヤ人の苦悩と目指すものが、終わりの日に神が完成される救いの一部を体現しようと求めている姿にも見えてきます。
草創期のシオニズムにとって、迫害下にあるところからの脱却を求めていますが、預言者は数多く、奴隷状態からの解放を終わりの日の幻として伝えました。国を造らねばならないとする政治シオニズムは、ダビデの家からメシアが出てきて、神の国を建てるという幻に重なります。文化シオニズムであるヘブル文化の復興についても、ユダヤ人が長年の離散の生活から郷土に帰還し、かつての言葉、かつての生活を取り戻す幻も預言者は語りました。占領についての悩みは、寄留者に対して優しく取り扱わなければならないとする神の戒めに関わるものです。キブツに代表される農地開墾は、剣を鋤に変えるなど、約束の地が荒野に緑が、木々が、草木が、あらゆる農産物が取れるという幻に関わります。修正シオニズムは、イスラエル人が直面する、嫌になるほどの現実、すなわち「アラブ人が紛争をやめるのは唯一つ、イスラエル人は譲歩するつもりはないと悟ったときだ。」(365頁)という考えですが、聖書には戦いに勝利する時に「救い」という言葉が使われていて、「戦いをもって戦いをやめさせ、平和をもたらす」という神の方法に通じるものです。宗教シオニズムは、神に与えられた約束の地の境が明確に、預言者たちに啓示されました。けれども、これらは神の国であり、メシアが王であるところの、いわば神政国家でなければなりません。御霊が注がれて、人々が神の戒めを守る国でなければいけません。そうなると、シオニズムに無関心などころか、敵対さえしている超正統派の主張に重なります。
異邦人のキリスト者として、私たちはこれらのことを、キリストが来られた時に神の国として実現するのだということで心の整理をしています。そして今の関心事は、この恵みの福音を全世界の民にくまなく広げることです。また、モアブ人のルツのような、真っすぐな信仰、神から離れているところから、何もないところから神に従うと決める姿に反映されています。けれども、それは、ちょうど放蕩息子のような信仰であり、そのまま父のところに来て、受け入れられ、恵みを受けました。対してイスラエル人は、兄息子のように、またはルツの話の姑ナオミのように、初めから選ばれ、神のそばにいるがゆえに悶々と悩んでいる、と表現できるかもしれません。愛され、選ばれているがゆえの悩みと言えるのかもしれません。(ローマ11:28‐29)
一般教養と見識の定番となってほしい
訳者は、ご自身、ユダヤ教を学び、精通し、なんとユダヤ神学校で教鞭さえ取っている、神藤誉武(じんどう よぶ)氏によるもので、内容を熟知しているのでしょう、日本語が非常にこなれています。最後の「訳者解説」で、日本では一面的に取り上げられる報道や解説書を意識して、「パレスチナ難民問題の背景」「アラブ・イスラエルの領土問題の捉え方」「イスラエル国防軍の対応」の三つの点で、しっかりと基本中の基本を押さえた解説をしてくださっています。
最後に、徳留絹枝女史による記事をご紹介します。
ここに書かれている、ダニエル・ゴーディス氏ご自身からもらった、メールの返信の言葉は、あまりにも明白で、我々日本人が、最も恥じて、謙虚にならないといけない言葉となっています。ユダヤ人に限らず、どんな国や民に対してもそうであるべきですね。
「日本の長い歴史や文化を理解することなく、日本政府や日本国民の行動を理解することはできないでしょう。イスラエルも同じです。日本の方々には、日々の新聞の見出しを追うだけでなく、ユダヤ人の長い歴史と遺産、そして(祖先の地に帰るという)シオニズムが何千年にもわたるユダヤ人の夢と切望であったことを、理解してほしいと思います。」

「「イスラエル - 民族復活の歴史」ダニエル・ゴーディス著」への1件のフィードバック