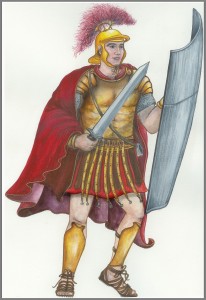クリスマス礼拝を今日、無事に終えました。とても簡素、けれどもしっかりとクリスマスの讃美歌を歌い、キリストの降誕の御言葉、それから聖餐にもあずかりました。内容は濃かったと思います。一人、初めての方も来られて、とても感動的でした。
少しだけ時間がゆっくりできたので、前から思っていたことでメモのようにして書き残したいことがありました。今、東十条バイブルスタディでテモテへの手紙第一を学んでいますが、そこにある箇所をまず紹介します。
「私がマケドニヤに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたは、エペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と系図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは、論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は、きよい心と正しい良心と偽りのない信仰とから出て来る愛を、目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、わき道にそれて無益な議論に走り、律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。(1テモテ1:3-7)」
二か月近く前に行われた、「カルバリーチャペル牧者「静養会」」において、バド・ストーンブレーカーさんが、「「安息」ルカ10章」のメッセージにて、大きく触発された内容を話してくれました。(31:00辺りから。日本語の通訳もあるのでぜひご自身で聞いてみてください。)
~~~~~~
羊を気遣う牧者の思いを持ってほしい。特に気づく分野は以下の三つである。その一つ一つは大変有意義なことだが、牧会の心がけを持っていないと、バランスを崩してしまう。 続きを読む 実が結ばれない教え