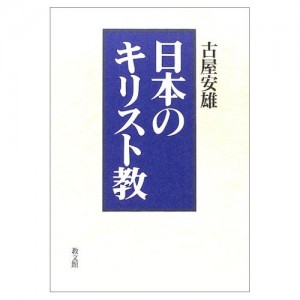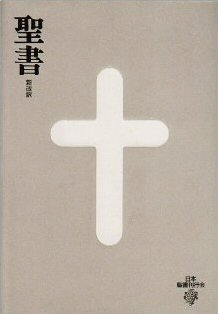前回は、聖霊の賜物の今日の働きと、今すぐにでも来られる主への希望について、聖書の言葉をそのまま信じていくところに力があること、そしてそれは使徒の教えと初代教会の姿勢を受け継ぐものであることを話しました。
ところで一昨日、二冊の古本をネットで注文しました。
キリスト教はなぜ日本に広まらないのか? 〈和魂洋才〉を追い、キリスト教抜きの近代化を進めてきた日本。その中で伝道し、事業を展開してきた教会各派と無教会、教育や社会事業などに例をとりながら日本のキリスト教の特質を検証し、将来を問う。
(愚直一筋の耶蘇坊主菊地一徳Kazunari Kikuchiさんの感想・レビュー)
古屋氏は次のような主張を持っていて、それが魅力的でした。「日本のキリスト教はインテリのキリスト教となっていて、大衆の方を向いていない、日本にキリスト教を広まるためには、インテリ的というエリート意識を捨てて大衆の方を向かなければならない・・」(古屋安雄「なぜ日本にキリスト教は広まらないのか―近代日本とキリスト教」)